
よい香り
謙虚さは、よい香りとなって
周りの人をよい気持ちにします。
傲慢は、嫌な臭いとなって
周りの人を不愉快にします。
外見をどんなにきれいにしても、
ひどい臭いがすれば台無し。
心を清め、いつもよい香りを
漂わせることができますように。
『やさしさの贈り物~日々に寄り添う言葉366』(教文館刊)
※このカードはこちらからJPEGでダウンロードできます⇒

よい香り
謙虚さは、よい香りとなって
周りの人をよい気持ちにします。
傲慢は、嫌な臭いとなって
周りの人を不愉快にします。
外見をどんなにきれいにしても、
ひどい臭いがすれば台無し。
心を清め、いつもよい香りを
漂わせることができますように。
『やさしさの贈り物~日々に寄り添う言葉366』(教文館刊)
※このカードはこちらからJPEGでダウンロードできます⇒

愛の響き
「わたしは良い羊飼いである。良い羊飼いは羊のために命を捨てる。羊飼いでなく、自分の羊を持たない雇い人は、狼が来るのを見ると、羊を置き去りにして逃げる。――狼は羊を奪い、また追い散らす。――彼は雇い人で、羊のことを心にかけていないからである。わたしは良い羊飼いである。わたしは自分の羊を知っており、羊もわたしを知っている。それは、父がわたしを知っておられ、わたしが父を知っているのと同じである。わたしは羊のために命を捨てる。わたしには、この囲いに入っていないほかの羊もいる。その羊をも導かなければならない。その羊もわたしの声を聞き分ける。こうして、羊は一人の羊飼いに導かれ、一つの群れになる。わたしは命を、再び受けるために、捨てる。それゆえ、父はわたしを愛してくださる。だれもわたしから命を奪い取ることはできない。わたしは自分でそれを捨てる。わたしは命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる。これは、わたしが父から受けた掟である。」(ヨハネ10:11-18)
「わたしは命を捨てることもでき、それを再び受けることもできる」というイエスの言葉が読まれました。「命を捨てる」というと、何か命を粗末に扱っているようにも聞こえますが、イエスがいうのは、自分の羊、自分に委ねられたかけがえのない大切な人々のためには、自分の命を捨ててもかまわないということ。それほどまでに誰かを愛することこそ、本当の意味で生きるということであり、命を捨てるほど誰かを愛したとき、わたしたちは永遠の命を与えられるのだということです。肉体の死など恐れる必要はない。愛することによってのみ、わたしたちは永遠に生きる。イエスは、この言葉を通してわたしたちにそう語りかけているのです。
「羊は、わたしの声を聞き分ける」ともイエスはいいます。神の愛を伝えるためならば、その人のために命を捨ててもかまわないというほどの思いが込められた言葉は、相手の心に必ず届くということでしょう。わたしたちの声を聞く人は、その声の中に込められたわたしたちの深い思いを必ず聞き取るのです。わたしたちが本気かどうかを、声から聞き分けることができるといってもよいでしょう。
それは、皆さんもよく分かるでしょう。たとえば、わたしが説教台から話すときに、わたしがその言葉を本気でいっているのか。「わたしたち一人ひとりがかけがえのない神の子だ」と本当に信じているのかを、みなさんはその声から聞き分けることができるはずです。わたしたちには、イエスの愛を感じ取り、聞き分ける力が与えられているのです。
わたしたちが教会に集まっているという意味で「囲いの中の羊」だとすれば、「囲いに入っていないほかの羊」もいます。教会に来ることがない人たち、日本社会の中でわたしたちが出会うほとんどの人たちのことです。その人たちにも、イエスの声を聞き分ける力があります。たとえば、友人から相談を受けてわたしたちが話すとき、キリスト教徒でないわたしたちの友人は、わたしたちの中に、本当に相手を思う愛があるか。その人のために、自分を差し出すだけの覚悟をもって話しているかどうかを、はっきりと聞き分けます。もしわたしたちの中にイエスの愛がないなら、相手は、わたしたちの話をただの「きれい事」としてしか受け止めないでしょう。しかし、もしわたしたちの中にイエスの愛があるなら、その愛は、必ず相手の心に届き、相手の心によい変化を引き起こすのです。すべては、わたしたちの心に愛があるか、相手のために自分を差し出す覚悟があるかにかかっているといっていいでしょう。
イエスの声を聞いたとき、当時のパレスチナの人々はその中に神の愛の響きを感じ取り、イエスの後に従いました。もしわたしたちの心に、相手のために自分の命を差し出してもかまわないというほどの愛、イエスの愛があるならば、わたしたちが出会う人たちも、必ずイエスの声を聞き分けるでしょう。まず、わたしたち自身がイエスの愛と出会い、心を愛で満たして頂くことができるように、そして、イエスの愛に満たされた心で人々のもとにでかけていくことができるように祈りましょう。
※バイブル・エッセイが本になりました。『あなたはわたしの愛する子~心にひびく聖書の言葉』(教文館刊)、全国のキリスト教書店で発売中。どうぞお役立てください。
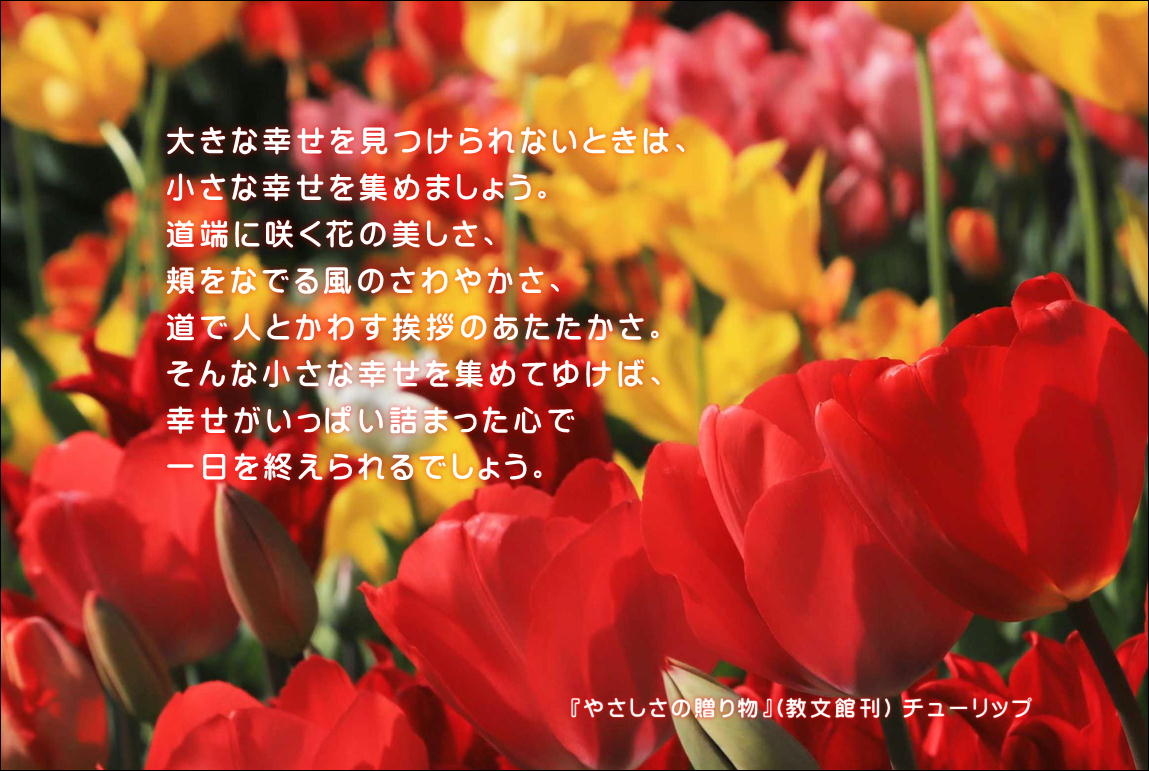
幸せ集め
大きな幸せを見つけられないときは、
小さな幸せを集めましょう。
道端に咲く花の美しさ、
頬をなでる風のさわやかさ、
道で人とかわす挨拶のあたたかさ。
そんな小さな幸せを集めてゆけば、
幸せがいっぱい詰まった心で
一日を終えられるでしょう。
『やさしさの贈り物~日々に寄り添う言葉366』(教文館刊)
※このカードはこちらからJPEGでダウンロードできます⇒

「罪の赦しを得させる悔い改め」
(そのとき、エルサレムに戻った二人の弟子は、)道で起こったことや、パンを裂いてくださったときにイエスだと分かった次第を話した。こういうことを話していると、イエス御自身が彼らの真ん中に立ち、「あなたがたに平和があるように」と言われた。彼らは恐れおののき、亡霊を見ているのだと思った。そこで、イエスは言われた。「なぜ、うろたえているのか。どうして心に疑いを起こすのか。わたしの手や足を見なさい。まさしくわたしだ。触ってよく見なさい。亡霊には肉も骨もないが、あなたがたに見えるとおり、わたしにはそれがある。」こう言って、イエスは手と足をお見せになった。彼らが喜びのあまりまだ信じられず、不思議がっているので、イエスは、「ここに何か食べ物があるか」と言われた。そこで、焼いた魚を一切れ差し出すと、イエスはそれを取って、彼らの前で食べられた。イエスは言われた。「わたしについてモーセの律法と預言者の書と詩編に書いてある事柄は、必ずすべて実現する。これこそ、まだあなたがたと一緒にいたころ、言っておいたことである。」そしてイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心の目を開いて、言われた。「次のように書いてある。『メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また、罪の赦しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に宣べ伝えられる』と。エルサレムから始めて、あなたがたはこれらのことの証人となる。(ルカ24:35-48)
弟子たちの前に姿を現したイエスが、「メシアは苦しみを受け、三日目に死者の中から復活する。また、罪の赦しを得させる悔い改めが、その名によってあらゆる国の人々に宣べ伝えられる」という旧約の言い伝えを弟子たちに思い起こさせ、「心の目」を開いてその真の意味を悟らせる場面が読まれました。
十字架と復活の真の意味とはなんでしょう。それは、イエス・キリストによってすべての罪がゆるされ、神と人間とのあいだに和解が実現したということに他なりません。イエスは、イエスを裏切って逃げるという罪さえゆるしてくださった。こんなわたしたちでさえ、イエスはあるがままに受け入れてくださった。その体験を通して、弟子たちは十字架と復活の真の意味を深く悟り、それを人々に伝える使命を与えられたのです。神の愛の本当の意味を、人々に伝える使命を与えられたといってもよいでしょう。
「罪の赦しを得させる悔い改め」という言葉が使われています。単なる後悔ではなく、罪からの解放をもたらす、根本的な悔い改めがもたらされるという意味だと考えてよいでしょう。では、人間は、どうしたら罪から解放されるのでしょう。罪はいったい、どこから生まれてくるのでしょう。
わたしは刑務所の教誨師をしていますが、罪を犯した人たちからよく聞くのは、「どうせ自分なんか、誰からも相手にされていない。自分が悪いことをしたって悲しむ人は誰もいない」という言葉です。だから、もうやけになって罪を犯したというのです。そうだとすれば、彼らの罪の根底にあるのは、「自分なんか誰からも愛されていない」という気持ちだといっていいでしょう。幼少期に虐待された体験や社会からの差別など、さまざまな体験を通して、彼らは、「自分は誰からも愛される価値がない。どうなってもいい人間だ」と思い込んでしまったのです。
彼らの罪の根源にあるのは、愛された体験の欠如、愛の欠如だといっていいでしょう。現に、彼らの多くが、自分を愛してくれる人と出会うことによって、そのような人たちの存在に気づくことによって悔い改め、罪から解放されていきます。家族との関係を回復することによって、あるいは親身になってくれる刑務官や教誨師などと出会うことによって、彼らは悔い改め、罪から解放されていきます。「こんなにも自分のことを思っていてくれる人がいるなら、もう悪いことをするのは止めよう。この人を悲しませることはできない」と思えるようになっていくのです。
罪のゆるしとは、弱くて意気地なしのこんな自分でさえ受け入れてくれる人がいるという愛の体験に他なりません。そのような愛の存在だけが、わたしたちを罪から解放してくれるのです。十字架と復活の出来事を通してイエスの愛に触れ、ゆるされたわたしたちの使命は、罪の中に閉じ込められている人を愛すること、わたしたちの愛を通して神の愛を告げることによって、彼らを罪から解放することだといってよいでしょう。イエスから与えられたこの使命、「罪の赦しを得させる悔い改め」の証人としての使命を果たすことができるよう、心を合わせてお祈りしましょう。
※バイブル・エッセイが本になりました。『あなたはわたしの愛する子~心にひびく聖書の言葉』(教文館刊)、全国のキリスト教書店で発売中。どうぞお役立てください。

大切な人のために
つらくて挫けそうなときでも、
大切な誰かの顔を思い浮かべると、
心の底から力が湧き上がってきます。
「あの人を守りたい」
「あの人の喜ぶ顔を見たい」
その思いが、あらゆる困難を乗り越える力を
わたしたちに与えてくれるのです。
『やさしさの贈り物~日々に寄り添う言葉366』(教文館刊)
※このカードはこちらからJPEGでダウンロードできます⇒

神のいつくしみ
その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへ、イエスが来て真ん中に立ち、「あなたがたに平和があるように」と言われた。そう言って、手とわき腹とをお見せになった。弟子たちは、主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。「あなたがたに平和があるように。父がわたしをお遣わしになったように、わたしもあなたがたを遣わす。」そう言ってから、彼らに息を吹きかけて言われた。「聖霊を受けなさい。だれの罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦される。だれの罪でも、あなたがたが赦さなければ、赦されないまま残る。」十二人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき、彼らと一緒にいなかった。そこで、ほかの弟子たちが、「わたしたちは主を見た」と言うと、トマスは言った。「あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、また、この手をそのわき腹に入れてみなければ、わたしは決して信じない。」さて八日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸にはみな鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、「あなたがたに平和があるように」と言われた。それから、トマスに言われた。「あなたの指をここに当てて、わたしの手を見なさい。また、あなたの手を伸ばし、わたしのわき腹に入れなさい。信じない者ではなく、信じる者になりなさい。」トマスは答えて、「わたしの主、わたしの神よ」と言った。イエスはトマスに言われた。「わたしを見たから信じたのか。見ないのに信じる人は、幸いである。」このほかにも、イエスは弟子たちの前で、多くのしるしをなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなたがたが、イエスは神の子メシアであると信じるためであり、また、信じてイエスの名により命を受けるためである。(ヨハネ19:20-31)
復活したイエスは、弟子たちに聖霊を送り、「だれの罪でも、あなたがたが赦せば、その罪は赦される」といって宣教に派遣しました。自分自身、神から罪をゆるされた者として、同じように罪の中で苦しんでいる人たちに神のゆるしを告げなさい。神の愛を、すべての人のもとに届けなさいということでしょう。
「ゆるす」というと、ちょっと上から目線のようにも聞こえます。しかし、イエスはここで、弟子たちに人を裁く権威を与えたわけではありません。なぜなら、実際にゆるしてくださるのは神で、弟子たちの役割は、神のゆるしを告げることだけだからです。弟子たちは、神がどれだけいつくしみ深い方なのかよく知っています。神は、イエスを見捨てて逃げ出した自分たちでさえゆるしてくださる方。わたしたちの弱さを知りながら、それにもかかわらずわたしたちを愛してくださる方だということを、弟子たちは身をもって知っているのです。
自分自身、ゆるされた罪人の一人として、神のいつくしみをまだ知らず、「自分なんかゆるされるはずがない。生きている意味がない」と思い込んで苦しんでいる人たちに、「いや、そんなことはありませんよ。神さまは、どんな罪でもゆるしてくださいます。何も心配する必要はありません」と告げること。神のゆるしを告げ、その人が安心して神のもとに立ち返り、神の愛の中で生きていけるようにすること。それが弟子たちに与えられた使命なのです。
わたしたちにも、同じように、神のゆるし、神の愛を人々に告げる使命が与えられています。「こんな自分でも、神はゆるしてくださった。この神の愛を、同じように自分を責め、苦しんでいる人たちに伝えずにはいられない」、そのような思いに駆り立てられ、人々の元に出かけていくこと。それがわたしたちの使命なのです。
しかし、残念ながら、わたしたちはときどき「こんな自分がゆるされるはずがない。わたしはダメな人間だ」という考え方に戻ってしまうことがあります。疑い深いトマスと同じで、目に見えない神の愛を、ときに疑ってしまうことがあるのです。そんなわたしたちのために、イエスは目に見える証拠を準備してくださいました。それが教会です。教会に行き、ミサに与ること、御聖体を頂くこと、信仰を共にする仲間と交わり、励ましあうことを通して、わたしたちは、「神はこんな自分でさえゆるし、大きな愛で包み込んでくださる」と実感することができるのです。「見ないのに信じる人は、幸いである」とはいいながら、見なければ信じられないわたしたち人間の弱さを知り、その弱さにそっと寄り添ってくださる方。それがイエスなのです。
今日は「神のいつくしみの主日」ですが、神のいつくしみを人々に告げるためには、まず自分自身が神のいつくしみを実感する必要があります。目には見えない神の愛を、目に見える教会の交わりの中で実感し、神のゆるしを告げるために出かけていくことができるよう、心を合わせて祈りましょう。
※バイブル・エッセイが本になりました。『あなたはわたしの愛する子~心にひびく聖書の言葉』(教文館刊)、全国のキリスト教書店で発売中。どうぞお役立てください。

幸せになる力
幸せな人とは、
見つける力、驚く力、
感動を人と分かち合う力、
与えられた恵みに感謝する力を
持っている人のこと。
特別なものは必要ありません。
誰にでもあるそれらの力を磨くだけで、
わたしたちは幸せになれるのです。
『やさしさの贈り物~日々に寄り添う言葉366』(教文館刊)
※このカードはこちらからJPEGでダウンロードできます⇒